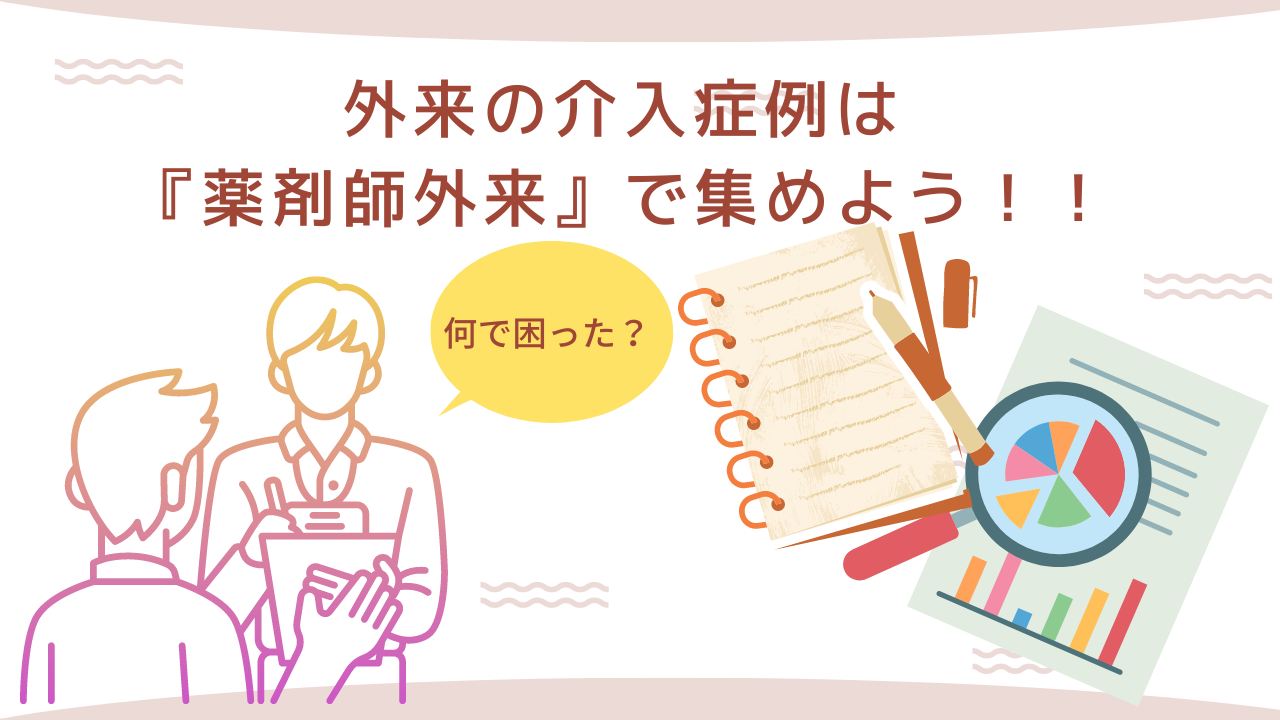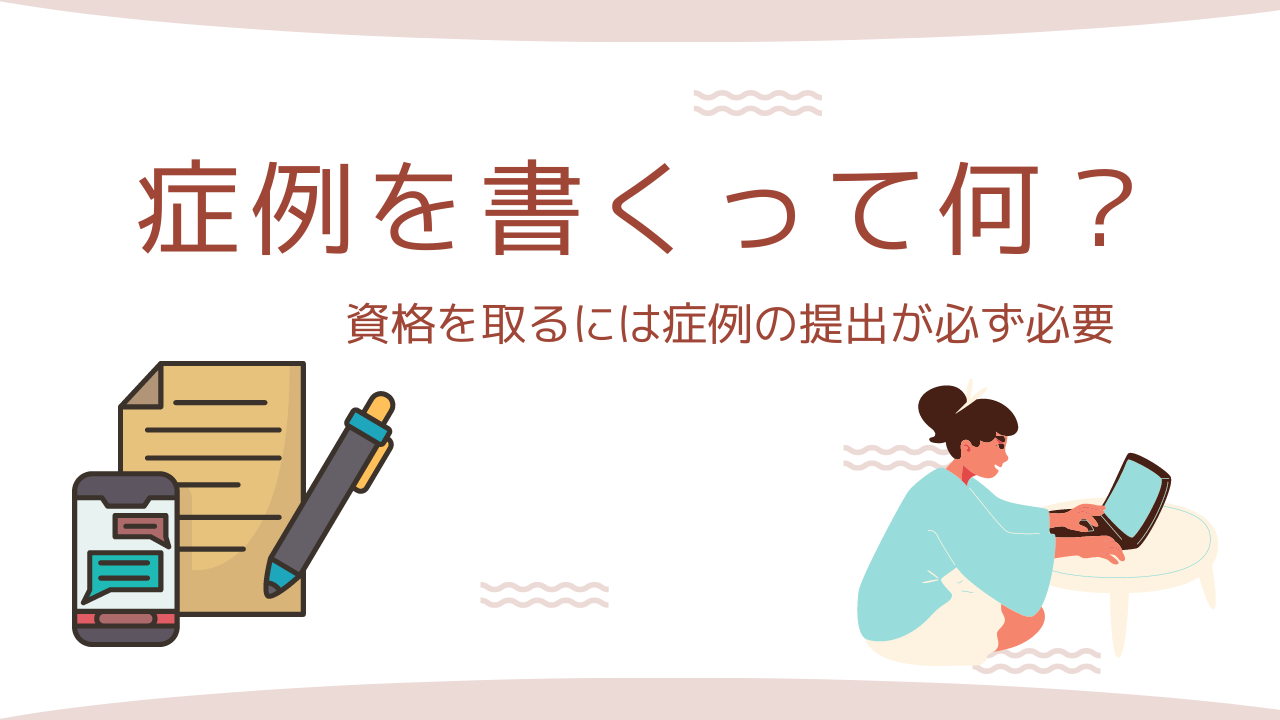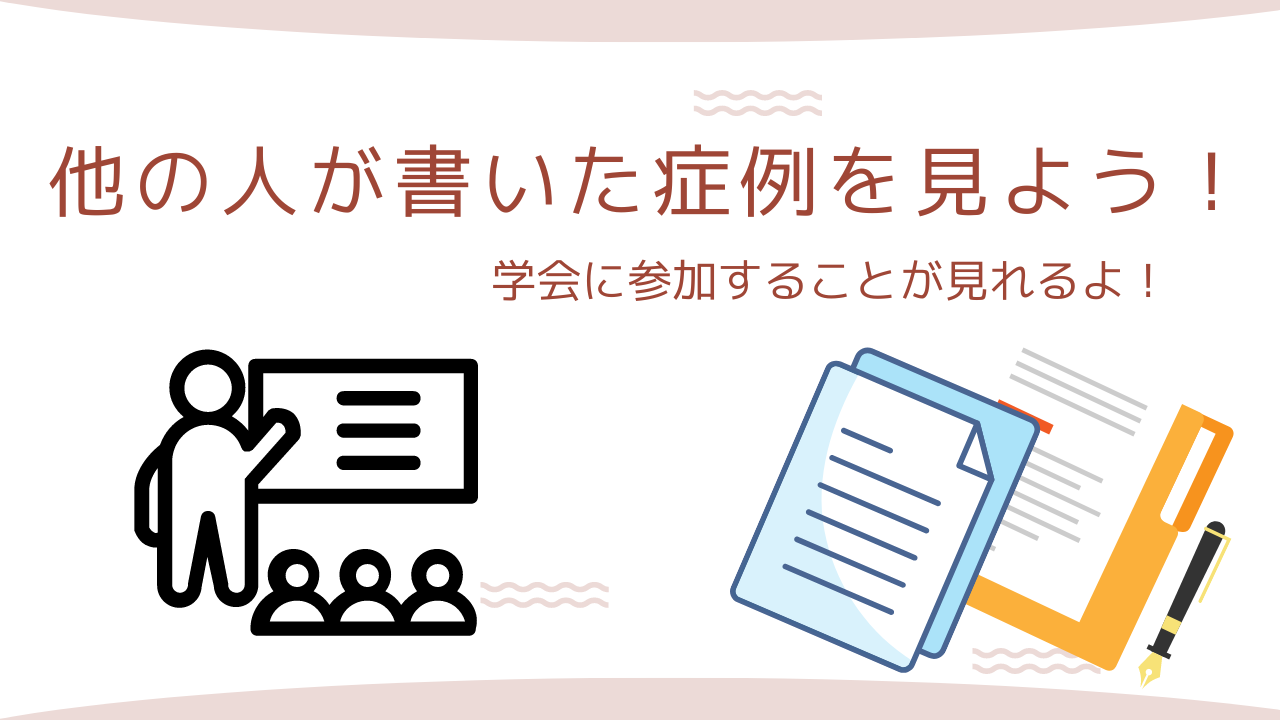外来がん治療認定薬剤師 症例の書き方・書く上で大事なこと
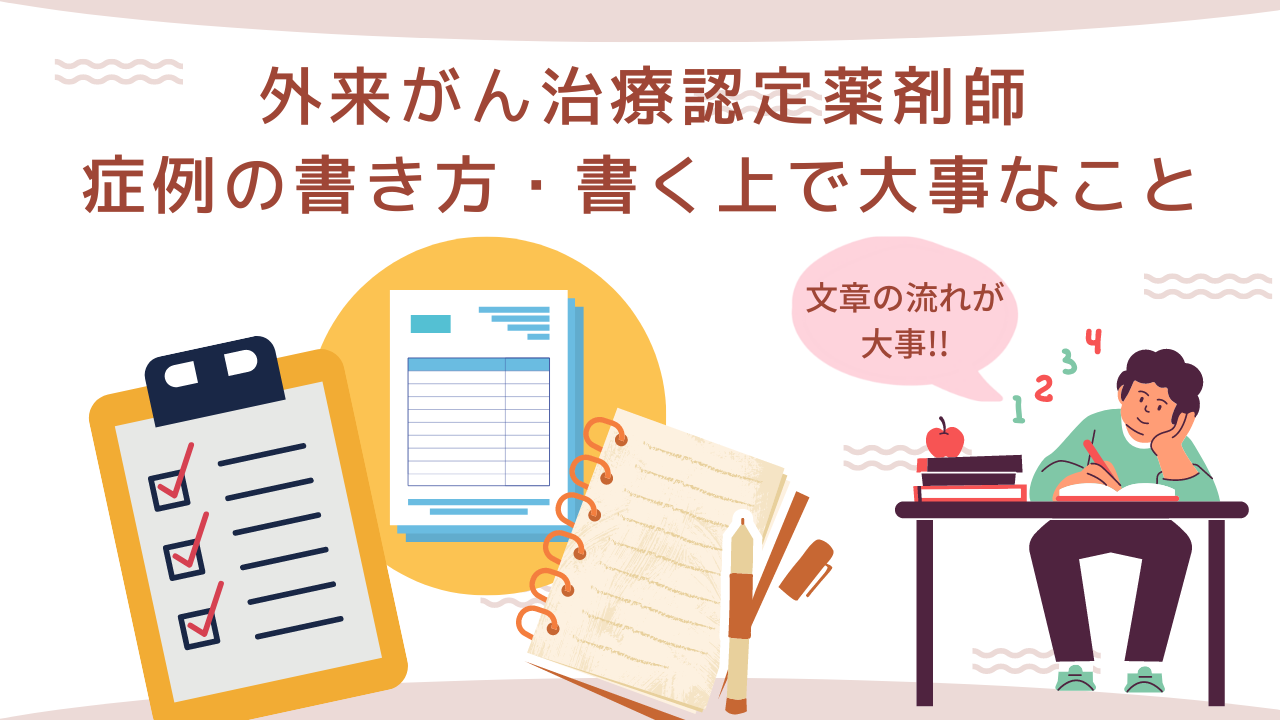
がんの資格を取得するには、自分が患者さんへ行った薬学的管理の要約(以下、症例と略します)を作成する必要がありますよね。
症例を書きあげるということが、資格取得の高いハードルになってる方も多いかと思います。
そこで今回の記事では、症例を書くにあたって重要な以下の点について解説します。
- 症例を書く時の文章の流れについて
- 症例中の文章の表現について
- 症例の文字数について
- 他人に症例を読んでもらう大切さ
- 症例を書く前に日本臨床腫瘍薬学会Webページの『要約の書き方』を読んでおく
さっそく見ていきましょう!
薬剤師の転職・派遣はファル・メイト目次
症例を書く時の文章の流れについて
症例を書く時の文章の流れは決まっています。簡単に言うと、
『どんな患者か(患者背景)』→『何で困ってるか(問題点)』→『何をしてあげた(介入内容)』→『その結果どうなったか(結果)』
ザックリですがこれを意識して書けば、それっぽい流れになります。
今回は、実際の『スニチニブ内服患者への介入症例』を使って見ていきましょう。
4年以上前の古い症例です。最近ではスニチニブはあまり見なくなりましたね。ご了承ください。
どんな患者か(患者背景)
まず初めに、症例の書き始めである、『どんな患者か(患者背景)』についての記載を見ていきます。
腎がんに対して腹腔鏡下左腎摘術施行。2 年後に再発・肺転移あり。その後、スニチニブ内服で治療中の患者。副作用確認のため定期的に薬剤師介入。
症例の出だしの文章はこんな感じです。
書く内容は、『何のがんですか』、『治療タイミングは術前・術後か進行・再発がんどっちですか』、『何の薬(レジメン)で治療中ですか』、ということを書いてみましょう。
また、病理情報が必要ながんの場合はそれも記載しておく必要があります。例えば、『乳がん』や『肺がん』を例にすると、
- 乳がん(ホルモン受容体陽性、HER2陰性)。閉経後であるが骨粗鬆症リスクを考慮し、タモキシフェン(TAM)で治療開始。
- 肺腺がん(EGFR遺伝子変異陽性)。オシメルチニブで治療中。
といったかんじで、今から『タモキシフェンについて記載しますよ!』ってなればホルモン受容体の発現や閉経の有無を、『オシメルチニブについて記載しますよ!』ってなればEGFR遺伝子変異の有無についての記載をするなど、患者さんが治療を行うにあたって必要な病理情報がある場合は記載するように心がけましょう。
何で困っているか(問題点①)
次に、患者が『何で困っているか』を記載した部分を見ていきます。
スニチニブ導入時に手足症候群の予防にヘパリン類似物質クリーム(以下、保湿剤)塗布の説明は受けており内服開始 3 週間は問題なく経過。内服開始 5 週後に足の裏に数カ所水疱と軽度の疼痛あり(Grade2)。
患者さんは何で困っているでしょうか。
困っているは、スニチニブの副作用と思われる手足症候群で、足裏に疼痛が見られることになりますね。この時に大事なのが、副作用をCTCAEのグレード評価で行いましょう。今回は疼痛を伴うためグレード2としています。
また、バイタル(血圧等)や検査値(肝機能、腎機能等)などに対して介入する場合は、実際の数値、単位、CTCAEのグレード(評価可能なもの)を記載しておきましょう。単位を書くのは忘れがちなので注意です。
例:血圧:140/80mmHg(Grade2)、腎機能:Ccr:120mL/min
また、薬剤名は基本的に一般名で記載していますが、名前の長いものは、ヘパリン類似物質クリーム(以下、保湿剤)のように、最初に正式名(略語)と書くと後半に登場するときは略語で記載も可能です。文字数が増えすぎる場合は参考に。一般的に広く使用される薬剤の略語であれば最初から使用しても問題ないかと思います。例えばS-1など。
何をしてあげた(介入内容①)
次に『何をしてあげた』についての記載です。
今後増悪する可能性も考慮しジフルプレドナート軟膏を主治医へ提案し了承された。患者へは症状が出ている部位へ 1 日 2回塗布することを説明し理解された。
薬剤師としてどんな介入をしたか書いていますね。基本的には主治医への処方提案などが多くなってきます。
今回は、疼痛部位に塗布できる用にステロイド外用剤の処方を主治医へ処方提案しています。この時に、主治医へ提案し了承されたという文章も大事かと思っています。
また、提案しただけでその後は何もしていないという印象を持たれないように、その後に患者さんへ使い方の指導を行った文章も入れています。今回の例だと、『症状が出ている部位へ 1 日 2回塗布することを説明し理解された』の部分になりますね。
他にも、提案後の使い方の説明の例として、
- 鎮痛剤(ロキソプロフェン):1日〇回まで使用可能と説明した
- 止瀉剤(ロペラミド):1日〇回で使用し、便秘傾向になれば中止するよう指導した
- うがい薬(アズレンスルホン酸):起床時、毎食後、就寝前に使用するように指導を行った
といったかんじで、私は提案した、で終わるのではなく薬剤の使い方の指導についても記載していました。
その後どうなった(結果①)
そして、その後どうなったか(結果)についての記載に繋がります。
2 週後、足の裏の水疱、疼痛は改善(Grade0)。保湿剤の塗布を引続き行うように説明した。
患者さんがステロイド外用剤をしっかり塗布した結果、足底の疼痛は改善していました。
薬剤師が介入した結果、症状が改善したのか、変わらなかったのかといった経過を必ず記載するようにしましょう(CTCAEのグレード評価や値を用いて)。
また、保湿の継続は、手足症候群の悪化予防に引き続き必要なので、こういった予防的な部分の指導も記載しています。文字数が許せば書いてもいいかもしれません。
何で困っているか(問題点②)+何をしてあげた(介入内容②)
そして次に、2つ目の問題点と介入に繋がります。
さらに2 週後、長距離を歩行した日が数日あったこともあり足の裏の水疱増悪あり(Grade3)。ジフルプレドナート軟膏の塗布でも疼痛が残っていた。手足症候群回復までの期間スニチニブの休薬とジフルプレドナート軟膏からクロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏へのランクアップを主治医へ提案し承諾された。また、患者は智歯の抜歯希望があることを確認していたため副作用として創傷治癒遅延のあるスニチニブ1週休薬後に抜歯を行うことを同時に提案し承諾された。
可能であれば1つの症例の中に2つ以上の介入があれば良いと思っています。しっかり1つの介入で深く関われているのであれば1介入でもいいんですが、今回のような外用剤の介入だけでは症例として弱い印象があります。
可能であれば、1つの症例に2介入入れてましょう。
2つ目の介入としては、手足症候群の増悪が見られGrade3となったため、適正使用ガイドの減量・休薬基準に従い、休薬の提案と、ステロイド軟膏のランクをstrongからstrongestへランクアップを提案しています。
また、親知らず(智歯)の抜歯を行う必要があったため、創傷治癒遅延の副作用があるスニチニブを1週経過後に抜歯を行うように提案し承諾されています。
その後どうなった(結果②)
そして、その結果の記載に続きます。これで最後です。
抜歯を終え、さらに1週後、足の裏の疼痛は改善(Grade0)。再び保湿剤のみを継続していただいた。スニチニブは1段階減量しスニチニブ 〇〇mg/day で再開。治療継続となった。
結果ですが、足底の疼痛が改善していることを確認。保湿剤を継続するように指導しています。
最終的に、1段階減量してスニチニブ再開となり継続となっています。
以上、症例の流れになりました!!
最初にも書きましたが、『どんな患者か(患者背景)』→『何で困ってるか(問題点)』→『何をしてあげた(介入内容)』→『その結果どうなったか(結果)』といった流れを意識して書くことが大事です。
症例中の文章の表現について
症例を書く時は、文章注の表現も少し意識しておきましょう。
簡単に言うと『血圧が上がった』と書くのではなく『血圧の上昇がみられた』、『患者が言っていた』と書くのではなく『患者からの訴えあり』みたいなかんじです。伝わるでしょうか。。。
こういった言葉の表現は、他の人が書いた症例を読んでみることで真似をすることができます。
他の方が書いた症例は学会に参加して読むことができますよ!詳しくは、『学会に参加して他の人(有資格者)が書いた症例を見てみよう』でも解説していますのでよかったら読んでみてくださいね!
症例の文字数について
『外来がん治療認定薬剤師』の症例審査へ提出する症例の文字数は、1症例当たり360文字以上600字以内で記載する必要があります。
私が初めて10症例を書き終えて、先輩に見てもらおうとしたとき、症例をしっかり読まずに全体をサラッと眺めただけで『やり直し!!』と突き返されました。
突き返された理由は、『文字数が少ない!!』でした。360文字以上は書いていましたが(たぶん360~400文字くらい)、まだまだ文字が記載できる空白のスペースが多かったのです。
文字数が少なく、空白が多いのことの何が悪いかというと、審査委員からの印象というのが私を指導していた先輩の考えでした。
最終的には、私は10症例全てを500~600文字の範囲で書きあげて提出しました。
文字数が多いから、必ずしも良いとは言えないかもしれませんが、確かにしっかりと記入枠内にぎっしり記載された症例と、余白が多い症例では、ぎっしり記載された症例の方が、丁寧に書いている気がして見て良い印象があります(個人的な考えです!)。
症例を記載するときは文字数が少なくなりすぎないように意識してみるのも大事かもしれません。
他の人に症例を読んでもらう大切さ
自分で書いた症例は必ず他の薬剤師(可能であれば有資格者)の先生に読んでもらいましょう。これがすごく大事です。
なぜ他の人に読んでもらうかというと、『他の人が読んで伝わるかどうか』を確認してもらいます。
私の先輩がよく言っていたのが、どれだけ素晴らしい薬学的介入を行っても他の人が読んで伝わらなかったらそれは審査で確実に落とされる、というものでした。
書いた症例は、一文が長すぎたり、時系列がわかりにくくて読みにくかったりしないでしょうか。
他の薬剤師の先生に症例を読んでもらって、感じた違和感を教えてもらいましょう。自分では気づけなかった部分がほぼ必ず出てきます。そして修正しましょう。
何回か『読んでもらう⇒修正する』を繰り返して提出できる症例になります。
私は『読んでもらう⇒修正する』を3回ほど繰り返して審査に提出しました。読んでくれた先輩には大変感謝しております!
ちなみに、『読んでもらう⇒修正する』を繰り返すには時間もある程度必要です。
余裕をもって症例を読んでもらうためには、早い段階から症例を書き始めることも大事ですね!
そして、他の薬剤師の先生に自分の症例を読んでもらうときは誤字脱字はないように自分で何度も見直ししてから読んでもらいましょう!
日本臨床腫瘍薬学会Webページの『要約の書き方も』読んでおく
日本臨床腫瘍学会のWebページで見ることができる『がん患者への薬学的介入実績の要約の書き方』では症例を書く上で注意すべき細かい注意点が書かれています。
当たり前のようですが、必ず読んでおきましょう。
『入院中の患者の介入は認めない』とか、『治験、臨床試験の症例は認めない』とか、『経過ばかり書かれていて介入があまりない』、『化学療法を行っていない疼痛緩和治療のみの症例は2例まで』などそもそもやってはいけないことが書いてますので一度はしっかり読んでおきましょう!
まとめ
症例の書き方について説明してきました。以下の簡単にまとめておきます!
- 症例を書く時は『どんな患者か(患者背景)』→『何で困ってるか(問題点)』→『何をしてあげた(介入内容)』→『その結果どうなったか(結果)』の順番になるように意識して書こう
- 文章の表現は他の人が書いた症例を参考に真似をしてみよう!
- 症例の文字数をは500~600文字の範囲になるように書こう!
- 書いた症例は必ず他の薬剤師に読んでもらおう!
- しっかり『がん患者への薬学的介入実績の要約の書き方』を読んで書き始めよう
参考になれば嬉しいです!頑張って症例を書きましょう!